島本理生の『夏の裁断』を読みました。2015年に文藝春秋から刊行され、2018年には文春文庫で文庫化されています。
島本は、何度も同じテーマで作品を書いています。それは、「人を支配し思い通りに操る男と、逆らうことができずに支配される女」です。2005年の『ナラタージュ』や2010年の『アンダスタンド・メイビー』、そして今回読んだ『夏の裁断』もその系列にあると思います。
『ナラタージュ』は大ヒットし、映画にもなりましたが、今考えても酷い内容です。自分の悩みと苦しみを言い訳にして、妻がありながら主人公である教え子と離れられず結局精神的に支配する教師、逆に暴力的に主人公を支配しようとする同級生・・・。もやもやを断ち切るように、最後は教師と決別して、別の人との結婚を選んで解放、という結論になっているけれど、結局主人公は「人を支配し思い通りに操る男と、それに逆らうことができずに支配される女」という構図からひととき逃げただけで、何も克服できていないなと思ったものです。
『アンダスタンド・メイビー』には、もっと何人もの「人を支配し思い通りに操る男」が出てきます。やはり主人公はそういった男たちにどうにもからめとられ、服従し続けます。ただ、『ナラタージュ』とは異なり、2つの救いが現れます。1つ目は無条件に自分を愛し助けてくれる同級生の存在、2つ目は自分の写真家としての才能と仕事です。2つの存在に支えられ、主人公は最後は自分の足で歩きだすのですが、でもやはり「人を支配し思い通りに操る男と、それに逆らうことができずに支配される女」という構図からひととき逃げられる場所を見つけただけで、主人公はやはりそれを克服できていないように思いました。
それに対して、『夏の裁断』では、主人公はそれを明確に克服しています。それを決定づけるのが、心理学を教えていた大学時代の恩師との会話です。
「あんまりだと、思ったから」
「なにが?」
だって、と続けると、声がふるえた。突き上げかけた感情が喉を締め付けて、すぐに散り散りになる。自分の顔が能面のように表情をなくしていくのを感じた。
「……それなら私、なんのために我慢して、声を殺して秘密にして、相手の思い通りになったのか意味がなくなるから」
「そうだね。意味は、なかったよ」
「先生?」
と私は思わず頼りない声を出して呼びかけた。
「意味なかったんだよ。菅野さんは我慢してきたけど、そこにはなにひとつ意味なんかなかった。とっくに全部忘れてるよ。やったほうは」
「本当に、なにもないんですか?」
ないよ、と教授はきっぱりと答えた。
「あなたが守らなきゃいけないと思い込んで背負ったものは不要なものばかりで、本当のあなたを殺し、得体の知れない不快感だけを残して去っていった。違う?」
ここを読んで、島本は、ついに解放されたのだと思いました。教授の言葉は、主人公の我慢にはなんの意味もなかったと告げる残酷なものですが、そこには『ナラタージュ』や『アンダスタンド・メイビー』にはなかった、本質的な答えが示されています。それを受け入れて、主人公は本当の意味で、新しい一歩を踏み出す。『夏の裁断』はそういう物語だと思いました。
僕は島本の作品の長所は、一つのことをものすごくたくさんの言葉を積み重ねて表現しようとしているところなのだとずっと思っていました。回りくどいぐらいに、何度も、違う言葉を積み重ねて。だからこそ、『ナラタージュ』や『アンダスタンド・メイビー』は分厚い大作になっていました。
ところがこの『夏の裁断』は、対称的に薄い本になっています。それは、今まで語っていたことを、ものすごく端的な言葉で、短く表現しているからであり、そしてそれは、島本を悩ませ続けたことに明確な答えが出たからなのかな、と思いました。もしかしたら、『夏の裁断』は島本がこだわってきたテーマを描く、最後の作品になるのかも、と思いました。
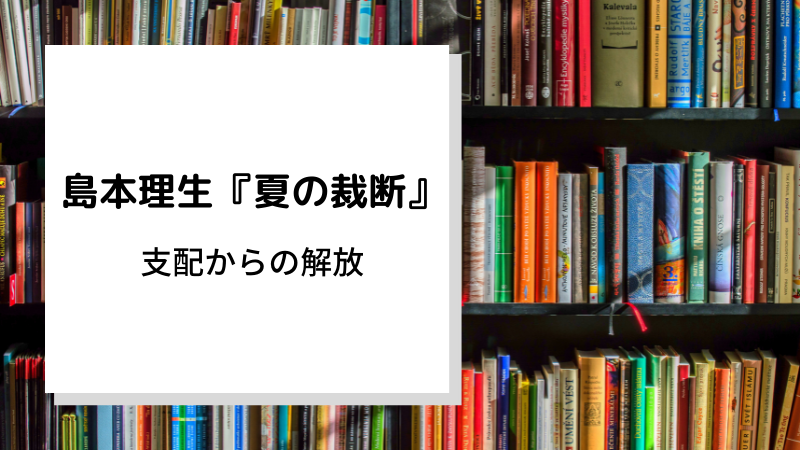
![夏の裁断 (文春文庫) [ 島本 理生 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1003/9784167911003.jpg?_ex=128x128)


コメント