引き続き直木賞受賞作を読んでおりまして、今回は大島真寿美の『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』を読みました。2019年上半期の受賞作です。2019年に文藝春秋から出版されていて、2021年8月に文春文庫で文庫化される予定です。
『渦』は江戸時代に実在した浄瑠璃作者、近松半二の人生を描いています。
独特の「跳ねるような」文体
『渦』は361ページと、ある程度ボリュームのある作品なのですが、すごい速さで読み切ってしまいました。それは内容に入り込めたという理由もあるのですが、それ以上に独特の文体が読みやすいからだと思いました。まるで「跳ねるような」文体なのです。
まず特徴的なのは、会話です。通常小説の会話は「」を用いて書かれます。もちろん『渦』でも「」の会話は出てくるのですが、「」を使わない会話もたくさん書かれます。たとえば、主人公の半二の新作をめぐる、座の仲間たちとの会話。
苦労しただけあって、思っていた以上にうまく書けたのだったが、いざやるとなったら座元の出雲は渋い顔だった。
p.104
なあ、半二、本水使うんはええが、ここまできっちりやらなあかんか。どこぞ一処に絞ってやるわけにはいかんのんか。
いかん、いかん。
半二の代わりに文三郎がこたえる。そんな半端なことさせてどないすんねん、せっかく半二がええもん書いてきたんや、あんたがやらせたらんでどないすんねん、こういうときはやな、でんと構えて、よしやってみなはれ、いうてたらええねん、と頑として譲らない。
出雲はためいきをつく。そうはいうけどやな、一面水浸しにするとなると裏方総出で、毎日、大儀やしな。
なんやて。
ぎろりと文三郎が出雲を睨む。
おいおい、作り話もたいがいにしてくれるか。誰が大儀やいうてんねん。え。誰もそないなこというてへんで。いうわけないやろ。みんなええもん拵えとうてうずうずしてるわ。勝手なこと抜かしてんと、すぱっとやらせたったらええんや。
文三郎がそう言い張る。
どや、みんな、そやろ。そやな。
「」を使わない平文でありながら、どこが会話なのか、また誰が話しているのかがはっきりしていて、なおかつ独特のリズムがあるところが素晴らしいです。大阪弁もリズムの一要素ではあると思うのですが、それ以上に改行や短い会話(「なんやて」)とかを挟む独特のリズムが、「」を使わない分と相まって、生き生きとした会話を際立たせているように思いました。
一方、主人公の半二が頭/心の中で考えたことを書く文体もまた、特徴的です。たとえば半二が突然現れた赤気(実はオーロラ)を眺めながら、亡き父を思い出す、こんなシーン。
以貫が生きていたら、なんといっただろう、と半二は赤い空を見ながら思う。
pp.220-221
呆れられただろうか。
しっかりせえ、と活を入れられただろうか。
ひょうっとして、この空の異変こそが以貫からの活ではないだろうか、と思ってみたりもする。
わしはこっちからちゃあんとみてるでぇ、という以貫の声。
あるいは点からとどく以貫の怒り。
いや、しかし、この不穏な空は、それよりも、やはり半二の心の奥の不安をうつしていると思う方がしっくりくる。
半二は空を眺めて、操浄瑠璃と己の行く末に思いを馳せた。
こちらもやはり、改行が多く用いられた文章になっています。思うに、自分が何かを考えているとき、長い文章で論理的に考えるというよりも、たくさんの短い思いを、順番に並べていることが多いような気がします。短文を積み重ねた散文的な思考を主人公と一緒にたどるのは、ものすごくリアルですし、また楽しいものでした。
江戸時代、浄瑠璃、一代記、といった少し重たい内容でありながら、この『渦』が読みやすくなっているのは、こういった会話や思考を描く軽妙な文体が、内容にとてもマッチしているからではないかと思いました。
「渦」とは何か
『渦』というタイトルは、パッと目を引くものですが、何のことなのかは本を手に取った時点ではわかりません。しかしそれは、読み進めていくと、明確に示されます。
客いうたかて道頓堀の客はむつかしいで。なんでもようみてはるしな、目が厳しい。あの人らの目がわしらにええ芝居を拵えさしよるともいえる。道頓堀、ちゅうとこはな、そういうとこや。作者や客のべつなしに、そうやな、人から物から、芝居小屋の内から外から、道ゆくひとの頭ん中までもが渾然となって、混じりおうて溶けおうて、ぐちゃぐちゃになって、でけてんのや。わしらかて、そや。わしらは、その渦ん中から出てきたんや。治蔵もそやで。宇蔵もな。あいつらはまさしく、この道頓堀が生んだ兄弟や。治蔵は渦ん中から生まれて、渦ん中へ早々に帰っていきよったんや。ああ、そやな、そやからこの渦には、きっと門左衛門も溶けとんのやろな。そやろ。治蔵の書いた国性爺は、門左の書いた国性爺からきてんのやで。ちゅうことはやな、あの並木千柳も、吉田文三郎も、みんなここに溶けてる、ちゅうことやないか。みんな溶けて砕けてどろどろや。な、そやから、わしらの拵えるもんは、みんなこっから出てくるのや。このごっつい道頓堀いう渦ん中から
p.201
この本を読んで初めて知ったのですが、当時の浄瑠璃や歌舞伎には、同じテーマを扱ったものがたくさんあるんですね。それは偶然ではなくて、たとえば浄瑠璃でヒットした作品を、もっと面白くしてやろうと歌舞伎の作者がアレンジした作品を作る。そしてそれをまた、浄瑠璃の作者がアレンジする、、、そういう流れで同じテーマが使われ、より良い作品に昇華されていくんです。
それは、著作権という概念がある現代では考えられないことではありますが、けどもしかしたら、そういった模倣とアレンジは、芸術の本質の一つなのかもしれないとも思いました。人間の思いつく/考えつく事柄は、きっと知れているし、限界がある。だからこそ、今僕らが読んでいる小説や映画や舞台も、ソポクレスや紫式部やシェイクスピアの焼き直しだったりするのかな、と思うのです。
作者が「渦」という言葉で表現したのは、そういう芸術の本質なのかな、と思いました。「模倣」とか「オマージュ」とか「承継」とか、もっとはっきりした言葉もありますが、そうではなくてもっと「溶けて砕けてどろどろ」になって出来上がってきた芸術を表すために作者が選んだのが「渦」なのだと思います。人類が時間をかけて作りあげてきたものが、なんだかよく形はわからないけれどそうやって残っていると考えると、すごく面白いし、ありがたいことだと感じました。
まとめ
正直とっつきづらいテーマと舞台ではありますが、ここで取り上げた独特の文体や、作者がテーマをものすごく明確に表現していることで、読みやすくかつ楽しい小説になっています。どんな人にも、何かしら発見があるぐらい、たくさんの要素が詰まっているので、読書好きの人にも、そうでない人にも勧められる本だなと思いました。
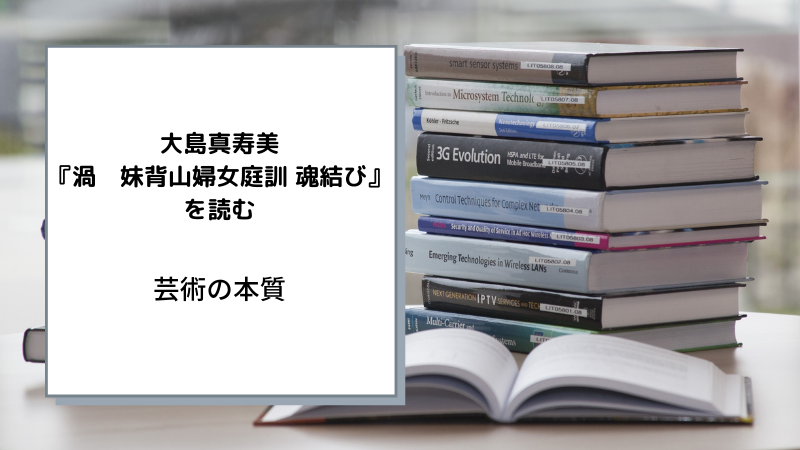
![渦 妹背山婦女庭訓 魂結び (文春文庫) [ 大島 真寿美 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7302/9784167917302_1_4.jpg?_ex=128x128)


コメント