僕はこれまで芥川賞受賞作はかなりの割合で目を通してきたのですが、直木賞受賞作にはあまり触れてきませんでした。もちろん娯楽作も好きではありますが、基本的に純文学が好きなのと、あとなにより芥川賞受賞作は『文藝春秋』の3月号・9月号を買えば全編が読めるのに対し、直木賞受賞作は『オール読物』を買っても全編が載っていない場合が多いからなのです。
なんですが、なんとなく思い立って、最近の直木賞受賞作に目を通してみることにしました。
今回は、門井慶喜の『銀河鉄道の父』です。2017年に講談社から出版され、同じく2017年下半期の直木三十五賞を受賞しています。2020年には講談社文庫で文庫化されています。
宮沢賢治を評論する小説
直木賞受賞作であるということ以外には、作品自体についても、また門井慶喜という小説家についても、なんの前提知識もなく読み始めましたが、まず驚いたのは、小説のスタイルでした。『銀河鉄道の父』というタイトルから、なんとなく宮沢賢治の父親についての話なのだろうとは想像していて、それはその通りではあったのですが、この小説は宮沢賢治の父政次郎の人生を描く小説であるとともに、政次郎の目線を通して賢治の生涯を描きつつ、賢治の作品を評論する小説なのでした。
たとえば賢治の妹との死別を詠った「永訣の朝」について、政次郎の視点を通して、こう評しています。
ほんたうにけふおまへはわかれてしまふ
あぁあのとざされた病室の
くらいびやうぶやかやのなかに
やさしくあをじろく燃えてゐる
わたくしのけなげないもうとよ
この雪はどこをえらばうにも
あんまりどこもまつしろなのだ
あんなおそろしいみだれたそらから
このうつくしい雪がきたのだ
(うまれでくるたて
こんどはこたにわりやのごとばかりで
くるしまなあようにうまれてくる)雪とは例の「あめゆじゅ」だろう。トシのもとめに応じて賢治が庭から二碗さらってきたい至誠のみぞれ、末期の水。
単行本pp.329-331
そのこと自体は事実そのままとして、問題は、括弧でくくられたトシのことばだった。文章語になおせば、
「また人に生まれるなら、こんなに自分のことで苦しまないよう生まれて来ます」
とでもなるだろうこの長ぜりふは、どう見ても、トシ自身のものではないのである。
政次郎は、思い出す。賢治はむしろトシを妨害したのである。政次郎が巻紙をかまえ、小筆をにぎり、
「言い置くことがあるなら言いなさい。」
と問うたら、トシは頭を浮かせ、渾身の力を以て口をひらこうとした。
生きたあかしを世にのこす最大かつ最後の機会だった。ところが賢治は政次郎をつきとばし、年の耳もとで、
「南無妙法蓮華経。南無妙法蓮華経」
ほろりと頭が枕に落ちた瞬間のトシのうつろな表情は、いまも政次郎のまぶたの裏にのこっている。それでいながら賢治は遺言を捏造した。トシの直身の意志を、おのが作品のために、
(ぬりつぶした)
政次郎は、本をばさりと放り投げた。
ぼくは宮沢賢治の専門家ではありませんので、これが史実なのかどうかはわかりません。あくまで小説ですから、べつに史実と異なっていたとしても問題はないでしょう。ただ、「永訣の朝」のように教科書にも掲載されるような有名な作品で、しかももちろんそこでは詩自体を直截的に味わうように教えられてきた僕らにとって、政次郎の目を通した門井の評論は、誰かにとっては不快なものでさえあるかもしれないけれど、僕にとっては新しい視点で面白いと思いました。
こういう、実存する小説家、あるいは作品を評論する小説がジャンルとしてあるのか、僕は知らないのですが、とても刺激的な試みだと思いました。
父性について
もう一点、これは父親の立場から、子供の一生を見守る、いわば父性の物語です。ゲイである自分にとって、現実的に自分が父親となることはないと思っていて、そういう意味で父性というのは自分とあまり関係のないものと思っています。
ですので、父性を描いた作品を読んでも、それは真実に理解できないものと思っていました。ところがこの本を読んで、自然と父親の目線で政次郎の思いをたどっていることに気づき、驚きました。
おそらくそれは、賢治が生まれた23歳のころから、賢治を看取った60歳のころまでの長い時間の心の動きを丹念に描いているからでしょう。長男だった賢治が生まれて初めて父となり、家業を守ることと、子供のやりたいことをやらせることの2つに引き裂かれていた政次郎の人生は、父性とは生来のものではなく、長い時間をかけて得ていくものなのだと思いました。
自分は実地でそういうものを得ていくことはできないのかもしれませんが、誰かのそれをたどることはできる。そう思うと、少し救われる気がするのです。
まとめ
『銀河鉄道の父』は、少し読む人を選ぶ小説かもしれません。まず、宮沢賢治の作品や人生について少しでも知っていて、何らかのイメージを持っていないと、門井ならではの評論によってそのイメージを覆される感覚を楽しむことができないと思うから、そしてまた、少し冗長に描かれる父と子の思いを一緒にたどることを面倒に感じる人には楽しめないかもしれないと思うからです。そういう意味では、万人が楽しむことのできる直木賞(と僕は考えていた)にこの作品が選ばれていることがちょっと意外でした。
一方で、そういう新しい世界を見せてくれる作品を僕たちに勧めてくれることこそ、直木賞の本当の目的なのかもしれないな、と思いました。
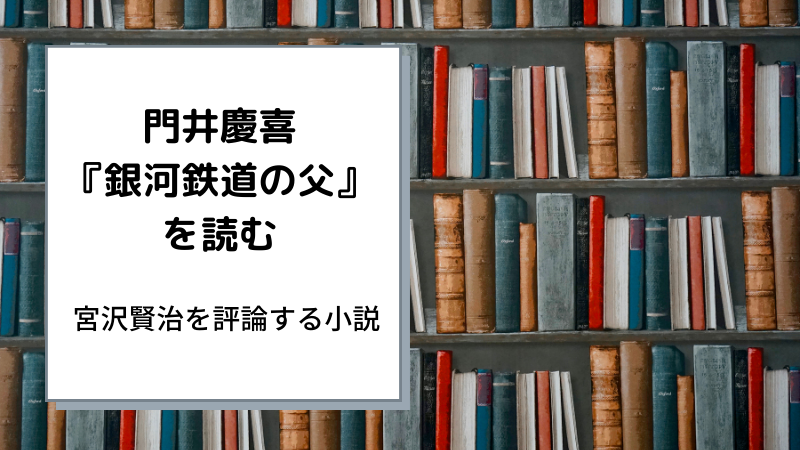
![銀河鉄道の父 (講談社文庫) [ 門井 慶喜 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3816/9784065183816.jpg?_ex=128x128)


コメント